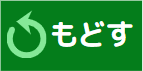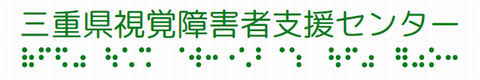12. 投稿 私流「安全歩行」について
津市 内田 順朗
- 白杖を持って歩行をし始めてから40年以上になる。残存視力があった頃は杖を前に出しているだけですれ違う人は私を避けていってくれるので、それなりに歩行は楽であった。視覚障がい者としての生活上の技術は視力低下とともに自分なりの情報収集や習熟により向上させてきたが、白杖歩行も同様に多少は上達していった。
また、折に触れて歩行訓練士による訓練も受けることができ、適切なアドバイスも大いに役立ってきた。
- 歩行訓練は、白杖の基本的な使い方に始まり、道路等の環 境把握の方法、危険の回避策、躊躇せずに援助を依頼すること、点字ブロックや音響信号機その他の安全設備の利用方法、そして歩行安全機器の活用などが要点ではないかと思う。
- 私は20年来盲導犬も使用している。白杖だけでの外出も少なくはない。行動範囲が広がるにつれ、メンタルマップの蓄積も重ねてきた。歩くルートの把握は大切な要素だ。家族やその土地の人に道路事情を聴いておくこともよくある。大いに参考にはなるが、視覚障がい者の立場からのアドバイスは期待できない。その点、折に触れて歩行訓練士の指導を受けると、ルートを確認し、安全かつ快適に目的地に行けるようになれるものだ。遠回りであっても安全なコースを選ぶ方が結局は自分のストレスも少なく悪天候などの環境変化にも対応できるというものだ。
最近視覚障がい者の鉄道踏切の通過について注目されている。奈良県での死亡事故以来、国土交通省からも対応策が出されたところではあるが、一朝一夕に解決できるものでもないし、完全な安全策でもなさそうである。それぞれの視覚障がい当事者のケースに応じて歩行訓練士による適切な指導・助言が本当に必要だと考える。
歩行訓練は各人の生活スタイルや必要性に応じて適切に受 けることが肝要であり、必要な時にそのような訓練が受けられる制度的な整備も必要である。
- 充分な訓練を受けたのち、利用できる補助具を活用すれば 良いと思う。
スマートフォンを活用した歩行支援が実用化してきている。「高度化ピックス」は交差点での信号情報を自分のスマートフォンでキャッチするものである。県内では40カ所以上に整備された。また、歩行者信号機の「赤と青を教えてくれるOKO」というものも試験的に運用されている。地図のアプリを音声化して「歩行ナビゲーション」をするものもある。
このようなスマートフォンを用いるシステムについて、視覚障がい者からの期待も大きい反面、それだけで安全に歩けるものだろうかという疑問視も多い。
上にも述べたように、歩行訓練を受けて自力歩行の技術を 習得した上でこれらのハイテク機器を活用するというのが基本ではなかろうか。例えば上記の「OKO」は音響の付いて いない信号機の赤と青を教えてくれるという点で、大いに助 かるものではあるが、横断しようとしている交差点の横断歩 道の傾向を正しく把握する歩行能力がなければ使ってはいけないと思う。決して信号機を探すアプリではないからである。以上長年の歩行歴と最近の機器の利用体験から感想を書いてみた。参考になれば幸いである。 (令和4年9月)