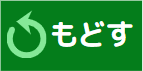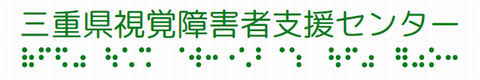11. 投稿 歩行支援アプリを体験
「スマホアプリで視覚障がい者の歩行を支援!まもなく実用化」
津市 内田 順朗
視覚障がい者が道路を安全に歩くときに欲しい情報はいろいろあります。白杖歩行あるいは盲導犬を使っての歩行にしても、自分の頭にメンタルマップが入っていることは必要だし、その時の歩行者信号の状況とか道路上を動いている人とか自動車の様子とか、そういうことを教えてもらえると、より安全に安心して移動することができます。
そのようなことをスマートフォンの機能を活用して視覚障がい者の道路移動を支援しようというアプリケーションが実用化されようとしています。
その一例が「アイナビ」です。昨年末に伊勢市で、ある実証実験が行われました。アイナビを搭載したiPhoneを首から提げて外宮前の参道を歩きました。
前方の歩行者信号機をスマホカメラが捉えると、その時の信号の赤とか青を音声で教えてくれるほか、横断歩道や点字ブロック・電柱などおよそ50種類の物体の存在も教えてくれたりします。目的の地点を予め登録をしておくとそれに向かう正しい方向も指示します。周辺の施設や建物の名称も教えてくれるので、楽しい散歩もできるようになります。
ただ、現時点でのGPSの精度とかスマートフォンの画像処理などの性能により、的確で素早い動きを期待することにはまだまだ課題はありそうです。もちろんアプリだけで危険を完全に回避してもらえるわけではないので、充分な白杖歩行のスキルは必要です。まわりの人たちからの支援も不要ということではありません。どうしても人に教えて欲しい場合は、このアプリからテレビ電話を通じて、提携しているサポートセンターのスタッフの支援を受けるということになります。まだまだ人の力
は大切です。この機能は有料となるようです。このアプリは福岡にあるコンピュータサイエンス研究所が開発を進めています。この春には無料で公開されるということです。
二例目は、上記のような多機能なアプリではなく、歩行者信号機の「赤と青」の状態を音声で教えてくれるというものです。「OKO」というアプリです。白杖歩行により信号機のある横断歩道の手前に来ることができれば視覚障がい者用音響が鳴っていなくても、スマートフォンを前方に向けるだけで信号機の「赤と青」の区別を音響で教えてくれます。このアプリは外国のものですが、日本語に対応し日本の信号機に合致するようにプログラムされています。本年中には一般公開されるとのことです。
私は上記の二つのお試し版を試していますが、信号機の判別については実用に耐えうるものと思っています。一般公開を大変楽しみにしています。
上記のアイナビのアプリを政府デジタル庁の河野大臣が体験デモンストレーションしたとのニュースが昨年末にありました。ニュースでは、河野デジタル相が実際スマートフォンを首からさげ、障害物や信号などを音声で聞いたり、また、オペレーターとつないでコンビニで買い物をする姿が紹介されていました。
これはアイナビを使って歩道を歩いたのちコンビニに入って買い物をするシーンです。品物を選ぶのはアプリでは無理なようで、遠方にいるオペレーターとテレビ電話の機能を利用して人的支援を受けたということですね。
河野デジタル相は、「ぜひデジタル技術で社会を良くしようと思ってる人に、どんどんデジタル技術を使ったいろいろなことにチャレンジしてほしいなと思う」また、「誰一人、取り残されないデジタル社会の実現に向け、様々な取り組みをしっかりバックアップしていきたい」と述べられていました。
このようなアプリが手軽に使えるように、私たちのデジタルを学べる環境を整えほしいものですね。